社会実装を加速する「凄腕プロ集団」の正体(WPI-ITbM)
「研究って、研究者さえいれば、できるものじゃないんです。長い目で見れば、実験をしている期間って、研究のほんの一部。それ以外の大部分には“伴走者”が必要です」
そう語るのは、自身も研究者とリサーチプロモーターの二足の草鞋を履くWPI-ITbM(名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所)の佐藤綾人さん。「研究」といえば、白衣を着てフラスコを振って……という姿が想起されるように、これまで実験こそが研究の全てであるかのように、クローズアップされてきた面は否めないだろう。
だが、研究成果を社会実装しようすれば、特許の申請や、多くの人々に技術に関心を持ってもらうためのアウトリーチなど、その活動は多岐にわたり、それぞれに専門スキルが必要となる。これらがうまくいかないがために、せっかくの研究成果を宝の持ち腐れにするわけにはいかない。
ITbMには、3つの事務部門がある。①総務・会計を担うマネジメントディビジョン、②広報・アウトリーチを担うリサーチプロモーションディビジョン(RPD: Research Promotion Division)、③知財化・社会実装を担う戦略企画ディビィジョン(SPD: Strategic Planning Division)だ。メンバーは理工系の修士・博士号の取得者で、かつ、それぞれに専門性を持ったプロ集団だ。
佐藤さんはITbMの設立当初から前拠点長の伊丹健一郎さんと二人三脚でRPDを設立し、その舵取りを担ってきた。同時に、ITbMの化学ライブラリーセンターの研究者としても研究に参加してきた経緯がある。その一つが融合研究記事で紹介した木下グループのプロジェクトだ。植物の環境応答に着眼し、気孔の制御技術として応用が見据えられている。
「研究の起点から実用化まで、全部を見届けることが夢なんです」
研究者の頭の中から始まり、予算を一緒に獲得し、ともに手と頭を動かし、その成果で実装までこぎつける。部署ごとにたらい回しにするのではなく、ワンチームで追うからこそ、研究の全体像を俯瞰できると佐藤さんは言う。
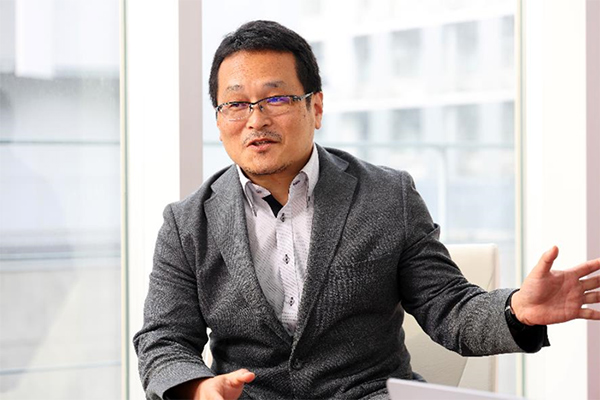
研究者の頭の中を「見える化」する
では、佐藤さん率いるRPDでは、どんな専門性を持ったメンバーが活躍しているのか。高橋一誠さんには「サイエンスデザイナー」という珍しい肩書がある。それもそのはず、ITbMで作られた、おそらく日本初のポジションだ。
高橋さんの仕事は「研究者の頭の中を可視化」すること。例えば、プレスリリースでは、研究成果を一つの絵に要約したグラフィックアブストラクトを手がけている。

 高橋 一誠さん リサーチプロモーションディビジョン(RPD)特任講師
高橋 一誠さん リサーチプロモーションディビジョン(RPD)特任講師
近年、情報を視覚化した表現手段としてインフォグラフィックが注目されている。より多くの人に研究に興味を持ってもらい、理解してもらう上で、図やグラフ、写真といったグラフィックは重要だろう。だが、佐藤さんは、ITbMにサイエンスデザイン専任のポジションを構えた理由はそれだけではないという。
「研究者がどう考え、何がしたいのかを視覚イメージで伝えることは、広報物やホームページを通じた一般の方々に向けたアウトリーチにおいて、もちろん重要です。その前段階で、研究費を申請したり、研究者間の交流を深めて融合研究を促進したりする上でも、大きな力を発揮するのです」(佐藤さん)
たしかに、構想を示す手描きの概略図・計画図(ポンチ絵)や、論文や学会発注のために成果をまとめたグラフィックであれば、多くの研究者は自分で準備しているし、その都度、外部のイラストレーターに発注することもできる。しかし「高橋さんは、客観的な立場でありながら、もう少し深い部分で根本的に関わっています」と佐藤さんは話す。
「1つのグラフィックをつくるのに、多いときでは、研究者と10回、20回とやりとりを重ねます。最初は研究者も言語化するのに苦労されるのですが、何度もやりとりをしていると、ビジョンが明確化していくのを実感します」と高橋さん。
たしかに、研究者自身の頭の整理になりそうだ。だが、基礎研究においては特に、具体的な応用のイメージが定まりきらない場合も多いだろう。研究者を理解することは難しくないのだろうか。
実は、ITbMに着任する前は研究者としての経歴を持つ高橋さん。ただ、専門分野はITbMの軸である生物や化学とはまったく違う領域だった。人間と機械の間のシステムに注目したヒューマンコンピューターインタラクションの分野で、自動車の運転支援に関する研究を行ったり、子どもの学習支援を目的に、体育館の床面にプロジェクションを用いた空間デザインを提案したりと「デザイン」という切り口で社会をさまざまな角度から捉えてきた。
「研究者の考え方、ロジック、コンセプトの描き方という大枠は捉えられるので、具体的な研究イメージが定まりきらない段階からでも協働できるのだと思います。自分が研究者だった頃は、いつも顔なじみと仕事をしていましたが、今は、毎日いろいろなグループの研究者と顔を合わせて、別々の案件を扱っているので、新鮮ですね。相手によって考え方も、進め方も違いますが、さまざまなフェーズの案件に同時並行で関わることで、ITbMの全体像も見えてきました」(高橋さん)
「生の声」を届けて、つなぐ
 三宅恵子さん リサーチプロモーションディビジョン(RPD)特任講師。過去に植物の繁殖生態に関する研究を行っていた
三宅恵子さん リサーチプロモーションディビジョン(RPD)特任講師。過去に植物の繁殖生態に関する研究を行っていた
もう一人、RPDでアウトリーチを担当する三宅恵子さんも、研究者のバックグランドを持つ人物だ。現在、三宅さんは、研究成果を広く社会に知ってもらうため、プレスリリースや広報物の原稿を作成するほか、学内外でのイベントを通じた施設・研究紹介を行っている。
「私の役割は社会と研究者の橋渡し役です。例えば、イベントを開催し、中高生をはじめ一般の方々の声を研究者にフィードバックしています。外からの声でモチベーションアップする気持ちが分かるので、接点を増やし、丁寧につないでいきたいです」(三宅さん)
 アウトリーチに関心を持つ大学院生とともにイベントの企画・運営を行っている様子
アウトリーチに関心を持つ大学院生とともにイベントの企画・運営を行っている様子また、ITbM全体として研究を進めていく上では、事務部門内での連携も大切だと三宅さんは話す。
「佐藤さんは科学の目線、高橋さんはデザインの目線、戦略企画ディビジョンの松島さん(このあと登場)は知財のプロと、事務部門のメンバーも、それぞれ立場と専門性が異なります。互いに情報共有することで、一つの研究を多角的に捉えられ、研究に対する理解も深まります。例えば、プレスリリースを作成するときも、佐藤さんが司令塔となり、私が文章、高橋さんは絵を担当。ITbMで生まれた分子が製品化したときは、それをホームページで掲載するので松島さんとも連携しています。バックグランドの違いから、ときに意見の相違もありますが、それも含めて、自由に言い合える雰囲気がITbMの魅力です」(三宅さん)
なお、三宅さんは対外的なアウトリーチに力を注ぐ一方、ITbM内においては女性研究者の活躍を後押しする場づくりにも貢献し、キッズルームの設置などにも携わってきた“ITbMらしさ”を形作るキーパーソン。ぜひ現場の実践例を紹介する「働く環境をトランスフォームする」もご参照いただきたい。
知財は「タイミング」を逃さない
ITbMの創設時から研究者と並走してきたRPD。融合研究が成熟し、社会実装のフェーズに入るプロジェクトが増える中で、特許申請や民間企業への技術移転に向けた調整など新たな業務も生じている。
そこで2016年にRPDからスピンオフする形で設置されたのが、戦略企画ディビィジョン(SPD : Strategic Planning Division)だ。SPDが独立して組織化されているのは、WPI拠点の中でも先進的。発明発掘、特許出願、国内外の企業との共同研究、ライセンス契約、事業化・商品化を目指した企業連携の戦略構築、産学官連携を進めるためのコンソーシアムの運営、さらにベンチャー企業の支援も行っている。
ITbM専任の弁理士として知財化や技術移転を担当する松島令子さんは、研究成果を社会に還元する役割を担っている。融合研究記事で紹介した木下グループの研究成果については、2018年に国際特許の出願も進めた。研究者と常日頃からコミュニケーションをとり、研究の進捗を把握することが欠かせないという。
「出願の範囲、出願するタイミングを相談しながら、どのようなデータを揃える必要があるのかを示します。論文発表と特許出願のタイミングを間違うと出願できないこともあるため、注意が必要です。改良や類似の技術が生じた場合も、その都度、発明者と相談しています」
近年、理工系の大学では研究者・技術者の卵である学生に、知財教育を行うところが増えているが、いざ実践となると「右も左も分からない」という人も少なくないだろう。ITbMでは松島さんが研究者に出願のプロセスや必要となる書類作成の相談に応じ、知財と技術移転の流れについての説明会を企画、運営するなど、留意点を伝えている。実用化に関心の高い研究者には個別対応も行っているという。
 松島令子さん 戦略企画ディビジョン(SPD)知的財産担当マネージャー、特任講師、弁理士
松島令子さん 戦略企画ディビジョン(SPD)知的財産担当マネージャー、特任講師、弁理士
一方で、研究者自身もまだ気づいていないニーズを見出す、あるいは、すでにあるアイデアを発明として「発掘」することも松島さんの重要な役割だ。
「ITbMは基礎研究を行う人も多いので、発明ヒアリングをすると『まだ何の役に立つかは分かりませんが興味がある現象を追っています』という研究者もいらっしゃいます。研究者の興味から始まったものであっても、せっかくの素晴らしい成果を社会貢献につなげなければもったいないですよね。そこで技術アイデアを提案すると、『そんな観点もあったんだね』と言ってもらえることもあります。研究成果を社会につなげる、やりがいのある仕事です」
融合研究記事でも紹介したように、木下グループの研究成果は、食料の安定生産や二酸化炭素の吸収(炭素固定)といった地球規模の課題解決に貢献することが期待されている。その研究の原点は、木下俊則教授の植物の環境応答性への興味にある。
木下グループの特任講師、相原悠介さんは「我々が想定していなかった使い方、アイデアが寄せられ、そこから共同研究に発展したり、また新しい基礎研究のテーマが立ち上がったりすることもあります」と話す。
異なる立場の専門家の視点、そして社会の方からの声が加わることによって、研究の枝葉は広がり、幹が太くなってく。まさに好循環が生まれている。
サポートではなく「協働」
前出の佐藤さんは「アンダーワンルーフで技術シーズと世の中のニーズの接点を探れることがITbMの強み。設立から約2年間は、名古屋大学内にはITbM棟がありませんでした。物理的な距離がなくなったことで、ITbM内のスタッフ間の心理的な距離も縮まりました」と話す。
「私もリサーチャーですが、まだまだ知らないことも多いですし、できないこともあります。『この先生に聞けば全部わかる』ということはないのです。研究者がいなければ研究はできませんが、研究者だけでもできません。それぞれ専門の能力、技能を持った人たちと協働していくことが必要です。だから、事務部門の私たちのやっていることは『サポート』とは言っていません。『協働』と呼んでいます」(佐藤さん)
対等な関係性で、互いの専門性に敬意を持ちながら協働する──オープンな雰囲気の中で一人ひとりのプライドがキラリと輝くプロ集団に出会った。ITbMはMix-LabやMix-officeを設置し、共同研究や異分野融合を促しているが、事務部門も含めて“Mix”されていると感じた。真の融合研究とは、単に学問領域を跨ぐだけでなく、もっと広く、社会における「異分野融合」をしていくことなのだろう。
【取材・文:堀川 晃菜、写真・図版提供:ITbM】
関連情報
過去記事
-

2023年3月29日
-

2021年2月8日
-

2021年2月3日
-

2021年7月29日

